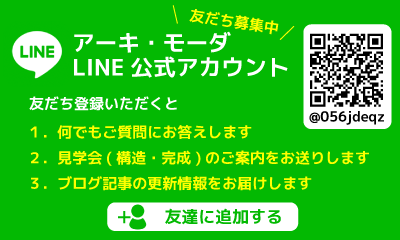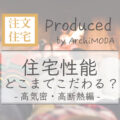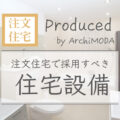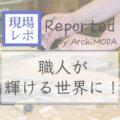2025.05.06 改稿
代表の鈴木です。
最近の住宅業界の話題は高気密・高断熱一色ですね!
何故こんなに盛り上がっているのかといえば、国の政策によるところと昨今の電気代高騰の影響が大きいのだと思います。
世界的に地球温暖化対策が急務となり、国も一次エネルギーの消費量を抑えるべく、住宅業界においても様々な優遇処置を講じて、省エネ住宅の普及を強く推進しています。住宅の省エネルギー化はCO2削減に寄与するだけでなく、光熱費の削減という住む方の経済的なメリットも実現させますし、さらに住む方の健康にも大きな影響を与えるとして、2重3重のメリットがあることを知れば盛り上がらない理由は見当たりません。
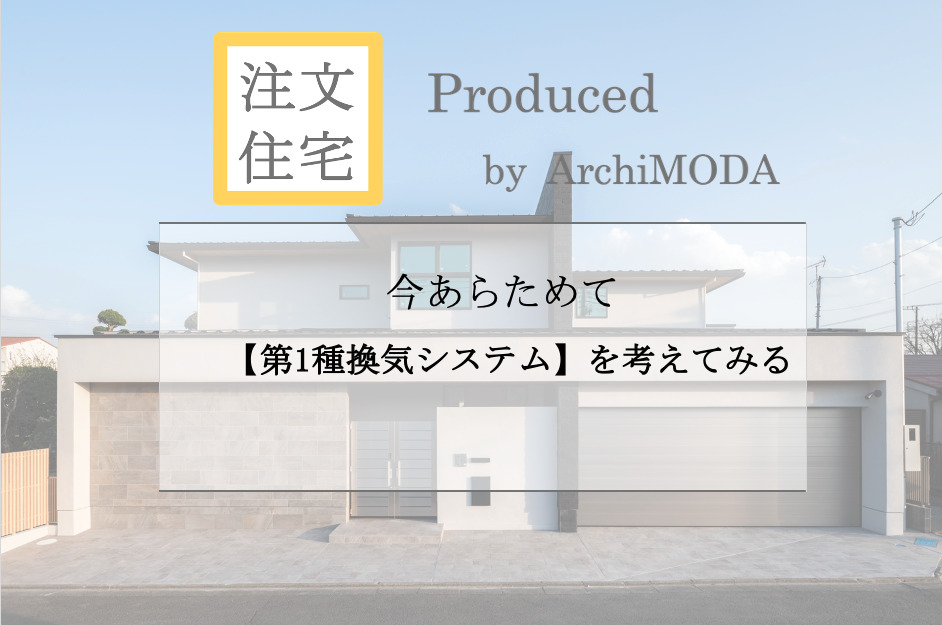
換気システムの選定が悩ましい!?
家づくりにおいて【高気密・高断熱】を突き詰めていくと、最後に選定で迷うのが換気システムです。
ここでいう換気システムは24時間換気システムの事で、第1種換気システム、第2種換気システム、第3種換気システムのいずれかを計画し、1時間で家の中の空気が0.5回入れ替わるようにすることが法律で義務付けられています。
世の中の主流は第3種換気システムで、コストも非常に安く計画できます。
しかし最近の高気密、高断熱住宅では、第1種換気システムが最適と理解されています。
第1種換気システムのメリットとデメリット
第1種換気システムの最大のメリットは、給気と排気の両方を機械制御する事で、換気効率を高めることができることと、熱交換機能を付加することで熱損失を最小化し湿度管理も最適化できるところです。
高気密、高断熱住宅は、冬場は特に過乾燥になる傾向があるので、湿度環境が補える第1種換気システムの採用が最適解と言われている訳です。
さらに第3種換気システムに比べ、外部フードがだいぶ少なくなるため、外観の美観向上にも寄与します。
ただし第1種換気システムは、設計計画上の難しさが多々あること、欠かせないメンテナンス手間や、何よりも価格が高くつくところが、採用にあたってネックになることがあります。
また皆さんの感心が高い【Ua値】においては、換気について考慮されていないため、Ua値には一切影響を与えません。
第1種換気システムにしてもUa値が良くなるということは無いということです。
第1種換気システムと第3種換気システムの価格差について
第1種換気システムについては「ダクト式」と「ダクトレス式」の2つの製品が存在しておりますが、ここでは一般的な「ダクト式」を中心に比較していきたいと思います。
第1種換気システムのシステム構成は、「本体+ダクト+ガラリ」という構成になっており、30〜40坪ほどの広さの家で計画するとシステム全体の定価は70万前後になることが多いと思います。もちろん施主様にはもっとお安く提供できるのですが、そこに施工費が加わりますので、材工でおよそ50〜60万ほどが現実的なラインといえます。
それに比べ第3種換気システムは、材工で5〜6万前後なので第1種換気システムに比べおよそ1/10の費用感です。
第1種換気システムを選ぶ意味
第1種換気システムと第3種換気システムの価格差が約50万前後あることをお伝えしましたが、果たしてこの価格差を受け入れるメリットがあるのかを検証していきたいと思います。
【金銭面の考察】
・頑張って高気密・高断熱を実現しても、国の法律で決められた換気システムが機能すれば、1時間で家の中の空気半分が外気と入れ替わってしまいます。
「せっかく温めた室温の空気を外気に捨てるなんてもったいない!」と思いますよね。
第1種換気システムの多くの商品は、本体に熱交換素子が存在し、80〜90%の熱交換が可能となります。
部屋の中の空気が20℃あって、外気が0℃であれば、熱交換によって外気の空気が16℃に変換されて室内に入ってきますので、とても魅力的かつ経済的な換気システムといえますので、当然ですが年間のエネルギーの削減効果は第3種換気システムよりも第1種換気システムの方が高いと言えます。しかしながら消費電力は第1種換気システムの方が大きいのも事実です。
ではどんなケースでも第1種換気システムのほうがお得なのでしょうか?
ここでは東京エリア(断熱区分区域6地域)で延床面積120㎡、断熱性能はHEAT20 G2(断熱等級6)を条件とし、東京電力の電気代、第1種換気システムの消費電力、メンテナンスコスト、エアコンのAPF、消費電力などを加味して計算してみると、第1種換気システムへの投資額50万が何年で回収できるかがわかります。
答えは実に60年以上!
ちょっと予想外だったのではないでしょうか。
これから60年の間に電気代も上がっていくはずで、上がれば上がるほど回収年は縮まりますが、それでも金銭的なメリットがあるとは言えないというのが現状です。
(東北、北海道などの寒冷地になれば金銭的な優位性も成り立ちます)
【快適性の考察】
・金銭的メリットは享受できないことはお話ししましたが、それでは第1種換気システムの採用は意味ないというわけではありません。
「快適性」という観点から見ていくと答えも変わってきます。
第1種換気システムのメリットとして「熱交換」と「除湿効果」の機能が挙げられます。投資額の回収は60年かかるかもしれませんが、その間の快適性が上がるのであれば決して無駄とは言えません。
高気密・高断熱を実現し、空調計画や換気計画をこだわる目的は、「経済性と快適性の両立」を手に入れることであって、金銭面(経済性)だけのメリットを求めているわけではないはずです。
【空気質の考察】
・快適性にも通じることですが、空気の質についても第1種換気システムにはメリットがあります。外気を取り入れる給気口は、第3種換気システムでは何となく心許ないフィルターが設置されていますが、第1種換気システムではしっかりとしたフィルターが装着されており、PM2.5や花粉が室内に入り込まないよう設計されております。
24時間換気システムは最適解なのか?
ここまでの解説で、第1種換気システムは価格は高いが価格以外のメリットが大きく、せっかく高気密高断熱の家を建てるならばぜひ採用したいと思うはずです。
もちろん私もそう思いますが、実務に携わり多くのお客様と接してきた経験から言うと違う考えも持つようになってきましたのでお伝えいたします。
そもそも24時間換気システムはなぜ必要になったのかという歴史的背景をおさらいしたいと思います。
今から20年以上前、当時建材や家具に使われていた接着剤から発生する有害物質(ホルムアルデヒド・他)や防蟻処理剤に含まれていたクロルピリホスなどが引き起こす室内の空気汚染が社会問題となり、シックハウス対策として24時間換気システムや内装制限などが2003年に法律にて義務化されました。
家中の空気を0.5回/hに入れ替えることが法律で決まったわけです。
そこからすぐにホルムアルデヒドを含む建材は姿を消し、防蟻処理剤の成分も見直されたことで、24時間換気システムの役割も終わったかに思えましたが、建物の高気密化に伴い今度は室内のCO2濃度上昇の懸念から今だ24時間換気システムが残っております。
CO2濃度上昇の緩和に必要な換気量は一人当たり30㎥/hと言われており、4人家族だと120㎥/hの換気があれば良いことになります。
一般的な住宅(仮に延床面積で120㎡)で検証してみると、建物の気積はおよそ280〜300㎥となりますので、24時間換気システムで求められる要求に当てはめると140〜150㎥/hとなり少々過換気となります。
ほぼいい線行っていると思われるかもしれませんが、この換気量が必要なのはCO2濃度が高まる時間帯、つまり夜に家族が揃い、就寝して翌朝また家族それぞれが出かけるまでの間に限られます。
そう考えると、日中家族が少ない時間帯も24時間換気システムを法律通りに可動させることは、非効率であるという考えも出てきます。
窓を開ける生活を否定できるのか
今の時代においては、窓を開けての換気はデメリットがメリットを大きく上回り、断熱・気密・空調・換気の観点からも推奨されておりません。
24時間換気システムも基本的に家中の窓をどこも開けない状況を想定したシステムです。断熱気密も同様で、エアコンなどの空調効率も窓は開けないことを前提として語られます。
しかしながら、設計時において窓計画は「明るさと風の通り」を重視した提案が主流です。施主様との打合せにおいて、「24時間換気システムがあれば家の中の風通しは不要です」と仰る方に出会ったことはありません。
日本人は窓を開けて空気を入れ替えたり風の流れを感じたりすることが昔から好きな国民なのです。
たとえそれが断熱・気密・空調・換気の観点から非効率だと理解していても、1日1回は窓を開けて新鮮な空気を取り込みたいという欲求を消すことはできないのではないでしょうか。
第1種換気システムが設計に与える影響
「第1種換気システムのメリットとデメリット」でも軽く触れましたが、第1種換気システムのダクト計画は設計者泣かせと言えます。
昨今間取りにおいて要望の多い、大空間のLDKを計画する際にはその天井裏には大きなサイズの梁が計画されますが、その下に第1種換気システムのダクト配管を通す空間を計画するとなると、相応の天井裏空間(懐空間)が必要となり、都市部の厳しい法規制で建物の高さが抑制される状況では、一部部屋の天井を下げるなどの対処が必要となるケースが出てきます。
また上下階につながるダクト配管を収めるためのパイプスペースも各階に1、2カ所必要となります。
このように空間設計に対する影響が少なからず出てくるのが第1種換気システムの最大のデメリットだと言えます。
大空間のLDKの計画のみならず、都市部の3階建てでの計画も同様のケースに悩まされます。
そしてもう一つ第1種換気システムが設計に与える影響として、建物の延床面積が50坪を超えるような大きさになってくると、第1種換気システムが2セット必要になってくることです。
2世帯住宅も同様です。システム金額も100万以上、ダクト配管も倍の数となりますのでちょっと現実的な提案とは思えません。
まとめ
断熱区分区域6地域に限って話をまとめていきたいと思います。
本来の24時間換気システムの役割が終わっている状況において、CO2濃度の軽減に必要な換気量や、どうしても窓を開ける習慣などを加味すると、24時間換気システムの計画は法律上必要だけれども、第1種換気システムをあえて採用する必要があるのかという疑問が残ります。
昨今建築費の高騰が続く中で、第3種換気システムと比べ、約10倍も費用をかけて第1種換気システムの採用を勧める理由も薄いと感じます。
たとえ第3種換気システムでも第1種換気システム同様に0.5回/hの換気は可能で、第3種換気システムの弱点と言われている「換気ムラ」についても、高気密住宅(C値0.7以下)では解消されます。
CO2濃度の抑制を重視するならば、第3種換気システムにて家族が集まる時間帯だけ稼働させることも可能ですが、第1種換気システムは、ダクト内の埃やカビの抑制の観点から稼働を止めることはできません。(一日中、一年中、一生止めることができない)ということは、永遠に第1種換気システムの電気代はかかり続けます。
また第1種換気システムは調湿効果が期待できることがメリットですが、冬場の理想的な温湿度を保てるほどの能力はなく、結局は加湿器の導入は必要となります。
生涯のメンテナンスコストも第1種換気システムの方がかかるでしょう。
以上の理由で、断熱区分6地域であれば第3種換気システムで十分なのでは?と思うところです。
それではまた!
★こちらの記事もおすすめ
【アーキ・モーダ LINE公式アカウント】
アーキ・モーダのLINE公式アカウントでは、「家づくりの質問になんでも答えます!」をやっております。ぜひ皆さんご登録をお願いします!
【YouTubeも始めました!】
是非、高評価、チャンネル登録お願いいたします!
〒176-0001
東京都練馬区練馬3-19-17 ニューハイツ練馬 1F
株式会社アーキ・モーダ
TEL:03-6914-8930
Mail:mail@archimoda.co.jp